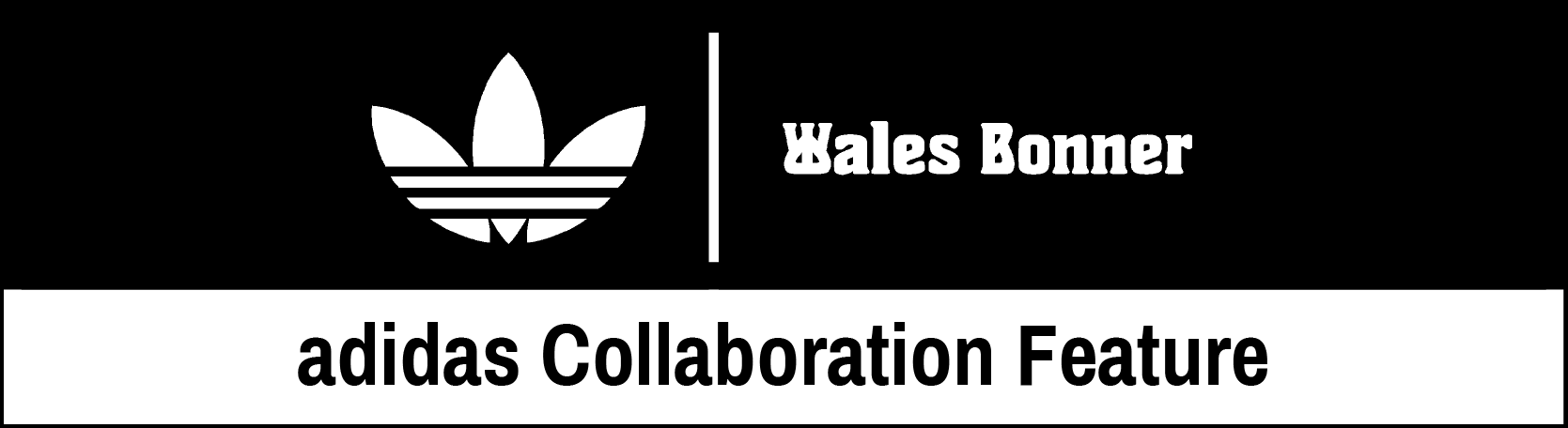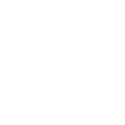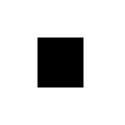「WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO」(ワイルドサイド・ヨウジヤマモト)という新プロジェクトが立ち上がると聞いて、なにか深いところに共鳴する感情があった。
ワイルドサイド――、すなわち、「ワイルドなほう」。英和辞典では、ワイルド(wild)には、「荒れた、野生の、未開の」などという訳語が充てられているけれど、ケンブリッジ・ディクショナリーに出てくる最初の定義は「uncontrolled」だ。つまり、(人間理性によって)制御されていない状態。それゆえ、人間の手の入っていない荒れた土地の様子の形容にもなれば、人間的理性を失った狂乱状態の意味にもなる。数年前にはやった筋肉自慢の芸人の決まり文句だった「ワイルドだろ~」のワイルドは、どこか危険な匂いを漂わせた男であることを誇示しようとして呼び出されたはずであったが、そのことばとは裏腹の、男のあまりにも安全な匂いが、ワイルドの語感とのギャップをつくって笑いになったわけだけれど、「ワイルドサイド」は本来、「危険な匂いがするほう」のことである。
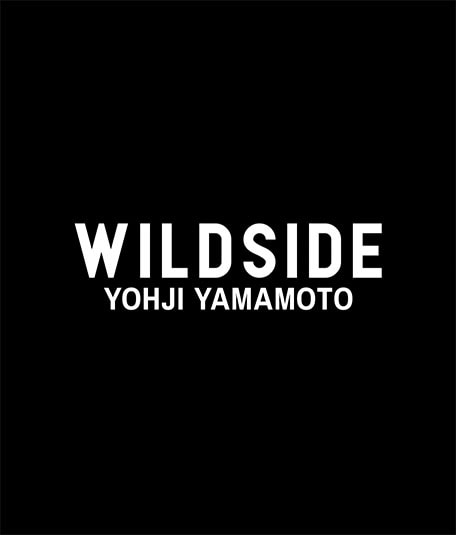
「WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO」プロジェクトの発表文は述べる。
「ファッション、アート、ライフスタイルを中心に様々なブランド、アーティストとの協業を行い、これまでになかったヨウジヤマモト社ならではのエッジの効いた世界観を提案するコンセプチュアル・プロジェクトです。特定のカテゴリーに捉われず、幅広いジャンルにおいて、特別なアイテムを次々にリリースしていきます」と。
このプロジェクトでは、ヨウジヤマモト社が他ブランドや他者と、ファッションのみならずアートをもふくむライフスタイル全般におよぶ広い分野で、積極的にコラボしたアイテムなり製品や作品なりを展開していく、というのである。「ヨウジヤマモト」の「ワイルド」化たるべきそれは、「ヨウジヤマモト」を(当然ながら)制御不能の状態に置くということではない。「協業する」ことによって他社と他者を積極的に招き入れる多声的(=ポリフォニック)なプロジェクトなのである。「ヨウジヤマモト」という単独者の視点によるひとつの発声(単声旋律=音楽=言語=思想)は、そこに依然として、そして厳として、存在するけれど、同時に他者(たち)の発声がそれに和して、多声的な音楽=言語=思想世界を出現させよう、というプロジェクトなのである。「ヨウジヤマモト」の境界が押しひろげられ、ドストエフスキーを論じたバフチン流にいえば、それぞれに独自の思想をもつ権利的に同等の登場人物たちがつくりだすドストエフスキー的小説世界のごとき多視点的な表現が、このプロジェクトから生み出されるアイテム、作品、製品に結実するにちがいない、と予想されるのである。ただならぬものが出現しそうだ、と期待しないわけにはいかない。
そして、もうひとつ。
この「ワイルド」化には、別の意味でも、どこかただならぬ気配がある、ということもいっておきたい。
というのも、「WILDSIDE」と聞いて、ルー・リードが1972年に発表した楽曲の「ワイルドサイドを歩け」(Walk on the Wild Side)を想起しないわけにはいかないからだ。耀司さんご本人が、そのことをどこまで意識したかは知らないけれど、まったく意識しなかったはずもない、と僕はおもう。
ルー・リードの曲は、1960年代から1970年代はじめにかけて、アンディ・ウォーホルのスタジオである「ザ・ファクトリー」に依ったトランスジェンダーをもふくむ「ワイルド」な面々が歩んできた/歩んでいる「危ない道」「ヤバい道」を、リリカルに歌う。そして、このリードの曲のインスピレーションになったのは、「スラム街の詩人」とうたわれたネルソン・オルグレンが、1956年に発表した『荒野を歩め』(A Walk on the Wild Side)である(この小説は1961年にエドワード・ドミトリク監督によって映画化されている)。
1929年にはじまった大恐慌時代のテキサスの田舎町の青年の、肉体と精神の放浪の遍歴をなぞる物語であるこの小説について詳述することは、本稿では禁欲しなければならないけれど、作者のオルグレンが、Macmillan Publishers版に寄せて述べていることばは、ぜひ紹介しておきたい。
「この本が問うのは、道をあやまった者たちが、一度として道をあやまらなかった者たちよりも、ときにより大きな人格の人間として成長するのはどうしてなのかという問いである。そして、人間性を素直に信じていた者がなにゆえに人に傷つけられて苦しめられ、そのいっぽうでなにもかもを手に入れてみずからは他になにもあたえない人々が、人間をもっとも蔑むのはどうしてなのか、という問いである」
スラム街の詩人のこのことばは、かつて耀司さんをインタビューしたときに、坂口安吾の自伝的掌編である「風と光と二十の私と」に触れて耀司さんがいったことを思い起こさせる。安吾がちょうど20歳のときに小学校の代用教員を務めた1年間のことを書いたこのエッセイについて、耀司さんは、「すごく印象的だったのは、小学校の教師になって、悪いことをする子には悲しい理由があることがわかった。だから、悪い子はぜったいに叱らなかった」(「GQ JAPAN」2018年10月号)と、安吾が書いていたことであった、といったのである。
道をあやまって人間の名によりふさわしい人間になり、人間性のよきことを信じて傷つき苦しみ、悪いことをする悲しい理由をもつ子どもがいるこの多声的世界には、「サニー・サイド」だけでなく「ワイルド・サイド」がある。そして、ワイルドサイドは、存外、いいものかもしれないのだ。

1949年東京生まれ。編集者・ジャーナリスト。2012年1月-2021年12月「GQ JAPAN」編集長。2000年8月‐2011年8月「ENGINE」編集長。1989年‐1999年「NAVI」編集長。慶應義塾大学文学部中退。海運造船の業界英字紙記者を経て1984年「NAVI」創刊に参加。著書に『〇×(まるくす)』(二玄社)、『走れ! ヨコグルマ』(小学館文庫)、『スズキさんの生活と意見』(新潮社)など。2022年よりフリーのエディターおよびジャーナリストとしての活動を開始した。